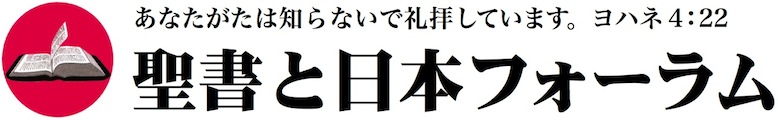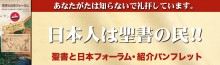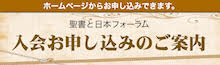武士は自分の職分をわきまえていた。「職分」というのは士農工商の農工商の三民に人倫の道を自ら手本となって知らしめることだった、と徳川時代の武士のなんたるかを教えた人がいた。時の儒学者山鹿素行である。この人に影響を受けた人に、浅野内匠頭長矩がいる。精神修養もせずにただ武家に生まれたがために、武士であるというわけなら、ガレージで生まれたら車になるのか?となる▼職分において世襲制が絶対条件なら山鹿素行は道義的人格形成を説くこともなかった。「大丈夫たる気性」(健全たる気性)を養うこととは、度量、志気、温籍、風度の四つで、度量とは天下の一大事にも動じないような器量の大きさ。志気とはささいなことは気にせず高い志をもつこと。温籍とはおんわで包容力の心をもつこと。風度とは卑屈で卑しい風情を見せないこと。この四つを修養するためには、まず自己の内面を正し、確立させることにより道義に合う気性を形成できるという▲21世紀の今ならポケモンゴーの隣人無視、内面空白の世界的風潮を一刀両断する〝刀〟をもって斬る現代サムライの出現を期待したい。素行は言う。行動、飲食、衣服、持ち物なども慎むことが威儀を高める、と。
著者紹介
- 聖書と日本フォーラム会長。聖書日本キリスト教会・登茂山の家の教会牧師。三重県志摩市在住。
Latest entries
- 2024.07.15雲の柱2024年7月 オーケストラの指揮者
- 2024.06.07雲の柱2024年6月 自由の律法
- 2024.05.12雲の柱2024年5月 裏切りは信頼に泥を塗る
- 2024.04.18雲の柱2024年4月 絶妙なるバランス